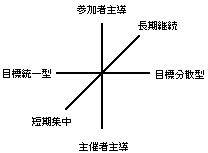
〈論文〉
学生主体の教育実践活動の成立・継続過程とその分類
−信大YOU遊サタデーの足跡から−
林向達 岡崎女子短期大学
土井進 信州大学教育学部
The type, and Beginning and Continuing Process of
Educational Practice Activities by University Students
RIN Kotatsu: Okazaki Women's Junior College
DOI Susumu: Faculty of Education, Shinshu University
【概要】
本研究では、1994年度から始まった第1期信大YOU遊サタデーから1997年度の第4期までを一つのまとまりとして捉え、学生が主体となって運営し続けてきた教育実践活動の変遷を整理する。ここから活動の継続過程について一般化を行ない、同様な教育実践活動を分類するための「人」「場」「時」を軸とした分類座標を提示する。
【キーワード】教員養成 教育臨床経験 教育実践活動 体験活動
1 目的
信州大学教育学部で行なわれてきた「信大YOU遊サタデー」を事例として取り上げ、活動の継続過程に焦点を当て考察を行なう。そこから継続過程に見られる要素を一般化し、分類に際して必要な基軸を抽出する。新規活動の成立や継続する際の一指標として役立てられる分類座標を提示することが本研究の目的である。
以下、各期毎にまず活動要素を一般化して挙げ、それから具体事例を記した。最後に各期毎の考察を踏まえ、活動の分類に関係する3つの要素を取り出してみる。
2 信大YOU遊サタデーの軌跡
2-1 第1期(1994)−無からの創造
・学生側の声と学部教官側の声の取り結び
・教育実習経験者を中心とした募集(3、4年生)
・学生個人の得意分野を講座化
・準備作業の短期集中
・活動理念やイメージの明確化
・学生スタッフへの情報提供の充実
学生を主体とした教育実践活動の始まりは、学生と学部が各々に持つ現状への不満と前向きな声を取り結び、集約したところにあった。着目すべきは、附属施設というどちらかといえば第三の立場に立つ者によって、それがなされたという点である。活動に関する様々な責任をこのような第三者が積極的に請け負う姿勢によって、活動の実現が促されたと考えられる。
また、当初からすべての学生を取り込もうとせず、教育実践への関心が高くなっている学年に焦点化して募集し、活動の要となる講座題目を希望者自身に委ねた。これにより、活動の大まかな筋が早期に出来上がることとなる。
大掛かりな催しを準備するためには、十分な時間をかけ綿密な計画を立てることが定石であるが、学生達は毎年進級・卒業を迎えるという制約があり悠長には構えられない事情がある。必然的に短期間による準備を迫られるが、これは参加学生の気力を集中させる点で効果的な状況だといえる。
また、活動の理念やイメージを早期に提示し、速やかに学生スタッフへ徹底させる必要性も生じる。活動の全体が散漫化せず、絞まりある活動展開ができるといえる。
2-1-1 具体事例
信大YOU遊サタデーは、1994年度「教育実習事前・事後指導」の場で、学生に向け賛同を呼びかけたことから具体的な動きが始まった。同年6月には実行委員会の結成。9月には第1回信大YOU遊サタデーが開催された
信州大学教育学部では、教員免許状取得のための講義・演習科目および3年次に4週間の教育実習を開設しており、実習を重視しつつも教員養成課程としてはごく標準的なカリキュラム内容であったといえる。1993年度には「教育実習事前・事後指導」科目が開設され、教育実習の質的向上と実習経験の総括にもさらに比重が置かれた。こうした講義によって、実習を経た学生達の声が徐々に鮮明になり始めたのであるが、その中でも「もっと子供達と接したい」という声は多くを占めた。
これとは別に、学部・教官側でも学部教育の充実を望む声は、従来から継続して発せられていた。その中の一つの声として、教育ボランティア的な活動を始めることはできないだろうかというものがあった。
学生と教官の2つの側からの声を結びつけるが如く「事前・事後指導」の場で活動の呼びかけをしたことが、信大YOU遊サタデー誕生のきっかけであることは上に述べた通りである。
募集対象としたのは、教育実習を経験した3、4年生が中心であった。理由は、子供達と接する活動をうまく運営するにあたり、実習経験が役立つであろうとの判断があったからである。また、実際に募集への関心が高かったのも教育実習経験者であった。しかしながら、準備過程の中で他の学年の参加にも配慮することが方向付けられた。長野市教育学部キャンパスには、1年生(松本キャンパスに在籍)を除いて、学部2〜4年生および大学院生が在籍している。教育実習経験者を中心としながらも、それをサポートするスタッフとして実習未経験者の参加を考えたのである。
具体的には次のような要領で募集が行なわれた。「事前・事後指導」受講の3年生に対し、参加と講座テーマの募集が行なわれた。この時点で、希望する学生が自らの得意分野を講座題目として提出する。同時に4年生などからも賛同者を募り、講座のリストが出来上がってくる。そして、最後に実習経験者以外からも参加を募った。講座題目を考えた学生を「キャプテン」と称し、基本的に実習経験者を充てた。キャプテンを支える「スタッフ」にそれ以外の学生を充てるという形をとった。
信大YOU遊サタデーは、その立ち上がりから開催までの期間が短かった。1993年度より教育実践研究指導センターによる呼びかけの原案が作成されていたとはいえ、本格的な準備は1994年6月の実行委員会結成からである。同年9月の第1回まで、3カ月間の準備期間内に、3年生は教育実習、学部も夏季休業をはさみ、実質的な準備時間はさらに短いものであった。
短い準備期間ながらも、実行委員会メンバーを中心に活動の理念やイメージ作りに力が注がれる。この活動がどういう位置づけのものであるか、また実際に子供達を迎えるにあたって活動の場をどのようなものとしてデザインしていくのか。回を追う毎に増加していく参加者や学生スタッフへの対応など含め、理念やイメージ作りは、常に試行錯誤を迫られ、ひっくり返りもした。さらに学生スタッフ間の連携をとるため、情報提供にも力を入れる。実行委員会が何を考え、どう計画を推進しているのか。多くの学生スタッフに提供し続けた。
(H6、9/10・10/8・11/12開催、学生数延べ152名・参加者数延べ544名)
2-2 第2期(1995)−土台を固め
2年目における特徴は、1年目との連携を重視する点である。
・前期スタッフの継続参加と活用(新4年生を中心として)
・活動理念や運営方針および手順の試行錯誤と洗練
・授業科目を通した連携
学生達が毎年進級・卒業する以上、学生メンバーの入れ換わりは避けられない。始動させた活動をどのように継続させるかは、活動を成立させること以上に難しい課題であろう。そのためには前年の活動をある程度総括し、様々な課題を今年へと引き継ぐことが、第一に考えられる手立てである。学部に継続在籍している学生達に引き続き参加してもらい、活動の継続を促すことも必要となる。前期スタッフの活用である。
1年目と2年目の継続に特化すれば、活動全体の理念や運営方針および手順などの整理を重視する必要がある。1年目が活動を短期集中的に始動させ、活動理念やイメージの明確化も実践の中で同時に展開させた状態にあるならば、今一度、それを整理し直さなければならない。その上でさらに試行錯誤をし、目標と現実に挟まれた中で位置づけを繰り返す。これは活動が続いていく限り平行して行なわれる努力である。
また、常に活動の基盤を鍛えることによって、活動に新たな試みを導入するチャンスが生まれる。活動を持続させるには適当な変化や新味ある企画を加え、学生スタッフの関心を高めることも重要となる。
さらに、支援をする教官を中心として、授業科目の側からも活動のサポートを行なうといった歩み寄りが大切になってくる。授業科目との緩やかな連携をとることによって、先のメンバーの入れ換わり問題を長期的に保管することが可能であるし、また、教育実践活動の内容を学問的な観点からも捉える機会が得られる。
2-2-1 具体事例
YOU遊サタデーの2年目は、前期での実践を見直し、問題点や活動そのものの意義について検討がなされた。第1期に3年生として参加した学生が4年生になっても引き続き活動に参加したことは大きな力となった。新4年生を中心として実行委員会が組織され、新たに学生スタッフと講座募集が行なわれた。
前期3回の開催実績を踏まえて運営手順にも試行錯誤が施されている。たとえば、講座申し込み方法の改善など。中には第1期で参加者に手渡されていた「修了証」を効率化を理由に簡略化することにしたが、参加者から以前の形の修了証を望む声が多く寄せられ、結果復活させるなどの出来事もあった。
また、理念について学生スタッフに広く理解してもらうために、以下の信大YOU遊サタデー「4つの柱」が掲げられた。
(1)触れ合いの場
(2)教育者としての実践と力量形成の場
(3)地域社会に開かれた学部づくり
(4)学校週5日制時代への橋渡し
これらは、第1期の混沌とした実践を見直し、この信大YOU遊サタデーという場が担い得るものは一体何なのかを整理した成果である。
講座の題目や内容についても前期からの蓄積部分があった。第1期のキャプテンが、第2期においても引き続き講座を開設する例も多い。また、講座内容の蓄積が新たな講座企画・内容の見本となって活かされた面も見逃せない。
さらにこの期では松本キャンパスでの開催が実現し「出張YOU遊サタデー」と呼ばれる、外部からの出前講座要請に応える試みも新たに加わった。
大学と地域社会とが触れ合う場を創造したこと自体に意義のあった第1期と異なり、第2期以降は、実践の内実が大いに問われてくる。そこで第2期では、講座づくりにも焦点を当て、指導案にあたる「遊学プラン」を軸としてキャプテン・スタッフのコミュニケーションの充実を図ったり、学部授業「教育実践学演習」との連携や実行委員会の定例化など、質的向上の努力にも少なからず目を向けた。しかし、学生スタッフ全体に効果的に波及するには時間が必要であり、一期中には十分消化されない面もあった。
(H7、5/27・9/9・10/14・10/28、学生数延べ315名、参加者数延べ871名)
2-3 第3期(1996)−屋根を設けた
第3期は、ほぼ出来上がった活動の枠組みを、豊かに肉付けする期だといえる。
・実行委員長
・学生スタッフ全体に仕事を割り振る運営
・当日活動における各所でのきめ細やかな配慮
・活動内容と成果の広報努力
・地域参加者の定着
学生主導による教育実践活動が、順調に進行するためには、求心力となる実行委員長の人選は、毎期重要な課題である。人選において考慮すべきことは、活動の運営経験も重要であるが、何よりも活動や参加者全体を見渡すことが出来るか否かといった人間力が面も大切となる。活動を滞りなくこなす事務的なタイプよりは、全体の雰囲気を盛り上げ、参加者を大切にする人物が長として好ましい場合が多い。これは、学生による実践活動が理屈よりもやる気によって支えられていることを浮き彫りにしている。
長の性格は同時に学生スタッフ全体の性格にもつながってくる。当日の活動をする際に、会場の環境を子供の目線で捉えられるかどうかの配慮などは、学生スタッフ全体の参加姿勢が反映して表れるものであり、ひいては長の姿勢の反映でもあろう。
活動や組織規模が大きくなるにつれ、係間の仕事内容の相互理解が薄くなる傾向や増加した講座間で互いの活動を十分知る機会が少なくなってくる。こうした溝を埋めるため、スタッフ間の情報交換を頻繁にすると共に、当日の活動や講座内容をより幅広く知らしめる工夫や努力も必要であろう。
この時期まで来ると、地域の参加者が定着してくる。対外的な認知度もあがり、活動のおおよそが理解され始める。活動を継続させる要素として、地域参加者との連携を取ることも有効であり、キャプテン役を地域の人材にも求めるといった試みが考えられる。
2-3-1 具体事例
第3期では、これまでの土台の上に、活動自体をより豊かなものにしようという特徴を持っていた。この期では、長野オリンピック開催によるキャンパス工事や、信州大学教育学部の新たな教科目「教育参加」との連携といった難題が数多く降りかかってきたため、そうした状況に適応する努力もなされた。
この期では、YOU遊サタデー運営で常に問題となっていた特定スタッフへの仕事の集中化に対して「みんなで仕事をやろうDAYS」という活動を呼びかけ、大所帯となった学生スタッフ間のコミュニケーションを促し、仕事の分散化の一助とした。本部スタッフなど中心メンバーが、定期的に連絡を取り合い、また、その経過を全体の実行委員会などで広める。このようにして、なるべくスタッフ間のコミュニケーションを密にとる努力がなされていた。様々な障害を乗り越えられたのも、そのようなスタッフ同士の連帯にあったといえる。
さらにYOU遊サタデーでの活動が当日以後も広がりを持つように「HOW TO サタデー」という冊子を作成配布、様々な講座の教材紹介をするといったアイデアに取り組んだ。
これら試みは、第3期で登場した女性実行委員長による明確なポリシーが反映された結果であろう。実行委員長は、参加者や学生同士のコミュニケーションや活動の双方向性を重視していた。女性的なきめ細やかさをもって全体を見渡していたといえる。
YOU遊サタデーでは、第2期において「お父さん、地域で講座をひらきませんか」という講座を開き、地域の人材をキャプテンとして迎え入れる素地をすでに展開していた。第3期でもこの流れの中で、地域で活躍なされている方の協力を得て「何でも研げちゃう!刃物研ぎ」や「ガリガリ竹とんぼ」講座を開くなど、地域参加者との連携を実践した。
この期が目指した活動の豊かさは、毎期まとめられている実践記録冊子の内容にも反映されており、各係の仕事内容や今後の課題など、詳細な成果を残している。
(H8、5/25・9/14・10/12、学生数延べ396名、参加者数延べ700名)
2-4 第4期(1997)−住み始め
全体運営の形がほぼ整い、より本来の趣旨である教育実践に注力できる時期。
・過去の蓄積と活動の趣旨を再確認
・全体運営から教育実践に焦点
・外部との交流
1年目と2年目における活動の骨組み構築と3年目における肉付けを経て、活動の器をつくる努力から、その中身を充実させる方向へと転換する時期にさしかかったといえる。学生主導による教育実践活動とはいえ活動をスタートさせるためには、対大学・対教官・対学生同士・対地域社会などに向けて、活動自体の存在なり意義なりをアピールし、認知させる努力が必要となる。参加者・関係者の相互作用によって場を発展させるこの種の活動においては尚のこと重要である。よって活動初期の目標が、活動の場自体を成立させることにあったのは必然的なものといえる。
そして初期の目標がある程度達成されつつある時点で、次なる目標、つまり活動そのものが本来的に目指していた目標につまずきなく移行できるかどうかが問われてこよう。そのような目標意識が新たに加わった学生スタッフに共有されるためには、再度過去の蓄積と活動の趣旨を再確認もしくは再検討することが欠かせない。
活動を継続性を持ったものとして成立させるために費やされていた様々な準備作業は、「成長の場」を創造する方法論や技術論、準備に立ち向かう学生スタッフの内省を眼前にもたらした点で、それ自体意義がある。次に必要となるのは、そのような全体に対してのまなざしを自身の教育実践活動に転じていくことであろう。子供達を始めとした地域社会の人々を活動全体にどう巻き込んでいくかというマクロ的視点から、活動の内実においてどう個々人と対していくのかというミクロな視点へ比重を移すということである。
そして、触れ合い・成長の場が全国に展開されている中で、そのような場と場との交流をスタートさせることも重要となる。大きな目的を同じくする他の活動との交流や情報交換を通し、さらなる場の活性を期待できるからである。
2-4-1 具体事例
YOU遊サタデーのスタートは、子供達との触れ合いの場を増やし、学生が自分自身を磨ける機会をつくるという願いに端を発している。この本来の願いに注力できるようになったのは、第4期になってようやくではないだろうか。
すでに3年もの歳月を経た活動としてYOU遊サタデー自体の形は固まってしまっている。活動意義の問い直しの中でも、マンネリ化に対する言及が明確に現れてきている。こうした事態は、YOU遊サタデーを軌道に乗せることに目標を焦点づけていたこれまでの活動の流れからすれば停滞を意味するようにも見える。しかし別の見方をすれば、枠組みに力を奪われることなく、個々の講座での準備や努力に力を注げるようになったという利点も生まれているのではないだろうか。反省会の発言で、単なる感想ではなく講座実践の自己分析が増えたことなどに各人の活動の深まりが表れている。
しかし現実にはこうした転換が滑らかに行なわれていたわけではない。外部交流の一つとして第4期で精力的に取り組んだ「出張YOU遊サタデー」は、キャンパスで行なってきているYOU遊サタデー本体の内容を見直す重要な契機をもたらしたが、一方でその「出張〜」自体を遂行するためにエネルギーが分散し、本体の開催が惰性の上に流れていたのではないかという指摘も出ている。今後の大きな問題でもあろう。
外部からの期待は、文部省によって呼び掛けられた「教員養成フレンドシップ事業」の展開にも見られる。全国の教員養成学部・大学の学生と地域社会との触れ合いの場に対して助成が行なわれるというもので、YOU遊サタデーと目的を同じくする活動が各地で生まれた。そして他大学との学生同士による交流も始まり、場は一層広がった。そうしたネットワークの中での位置づけも考えていかなくてはならない。
器から中身への比重の移動しつつあるとはいえ、こうした様々な期待と課題の中で、活動はまた新たな形への変化のスタートを切ろうとしている。
(H9、5/24・9/27・11/8、学生数延べ281名、参加者数延べ647名)
(出張YOU遊サタデー3回分、学生数延べ58名、参加者数約950名)
3 活動継続に必要となる3つの視点「人・場・時」
以上4期を通しての変遷を考察した上で、次の3つの要素にまとめることができよう。
1.「人」 各人の「人間力」を軸に据える重要性。活動を一般化し論理的に記述する試みは大切であるが、その一方で、拭いきれない固有性も大切にしたい。活動の成功が、方法論でのみ達成されるのではなく、そこに参加した人間の力によって豊かなものとなるようにデザインしていくこと。
2.「場」 場を活性化させる視点の必要性。子供達や地域社会の人々と学生との触れ合いの場を設けるということは、単に同じ時間を同じ場所で共に過ごすことによってのみ達成されるわけではない。場全体を見通した上で自分なりの関わりを展開する必要がある。
3.「時」 活動の長期的な展望による継続。そのようにして初めて本来の趣旨まで到達できない。YOU遊サタデーもまた、マンネリ化の弊害を免れないが、その域に達して初めて、私たちが追究すべき課題が見出されるのではないかと思われる。
以上、3つの要素を踏まえて、次のような座標軸を設定することができる。この座標は、YOU遊サタデーに代表されるような学生を主体とした教育実践活動を種別化するために活かせると考えられる。
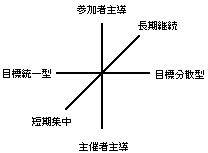
縦軸は「人」(参加者主導と主催者主導)、横軸は「場」(目標統一型[全体活動型]と目標分散型[講座制])、そして垂直軸に「時」(長期継続と短期集中)を配している。
この座標の中で、信大YOU遊サタデーは、複数の講座およびテーマを学生スタッフ側が事前に準備し、開催日一日で実践する点で「主催者主導・目標分散型(講座制)・短期集中」であるといえる。また他大学の中には、参加する子供達と共に活動内容を決定し、全体で一つの目標に向かって長期的に活動を行なう形もあり、その場合「参加者主導・目標統一型(全体活動)・長期継続」と考えることができる。
活動形態の次元における分類に留まらず、実際の教育活動の内容を座標の中に位置づけた場合、同じ活動でも随時座標移動が伴っていることにも留意したい。
適宜、活動の位置づけを分析することによって、現在の活動内容を反省したり、修正することができる。これは活動の継続性を高めるために重要な契機となろう。活動自体の停滞が生じた場合、活動形態のタイプを座標上で切り換えることによって、新たな刺激を生み出し、活動を再活性化させることが期待できるからである。
新規に教育実践活動を計画する際、また活動の方向性を定める際もこのような座標上での分析は役立つと思われる。
4 おわりに
以上、信大YOU遊サタデーの事例をもとに学生主導による教育実践活動の成立と継続過程を考察した上で、活動の性格を分類するための分類座標を提示した。
この時期、文部省によるフレンドシップ事業の促進により他大学においても様々な取り組み、試みがなされているが、そのような活動を成立・継続する際にこうした座標による位置づけの明確化と見直しが効力を発揮すると考えられる。
本研究は、信大YOU遊サタデーの教育体験活動としての内実を見るのではなく、むしろ教育実践活動としての外側とその運営面に関する考察を行なった。そのため取り上げた事例はあくまで部分であり、信大YOU遊サタデー全体を記述しているとは言い難い。分類のための座標が明らかになり、活動の位置づけが明確化したとしても、本質的な部分で教育体験の豊かさが満たされていなければ、この種の活動の意義は薄れてしまう。ゆえに活動の継続過程は、その内部の教育実践に強く結びついていることを自覚すべきであることを最後に指摘しておきたい。
【参考文献】
『平成6年度「信大YOU遊サタデー」の実践』信州大学教育学部附属教育実践研究指導センター1995年3月
『平成7年度「第二期信大YOU遊サタデー」の実践』信州大学教育学部附属教育実践研究指導センター1996年3月
『平成8年度「第三期信大YOU遊サタデー」の実践』信州大学教育学部附属教育実践研究指導センター1997年3月
『平成9年度「第四期信大YOU遊サタデー」の実践』信州大学教育学部附属教育実践研究指導センター1998年3月
土井進「教員養成学部における実践的指導力の養成」関東教育学会紀要第23号1996年
林向達・土井進「『信大YOU遊サタデー』における『人間力』の考察」信州大学教育学部附属教育実践研究指導センター紀要第4号1996年
「平成9年度教員養成学部フレンドシップ事業・シンポジウム」冊子、信州大学教育学部附属教育実践研究指導センター1997年11月28日
(1998年3月31日 受理)