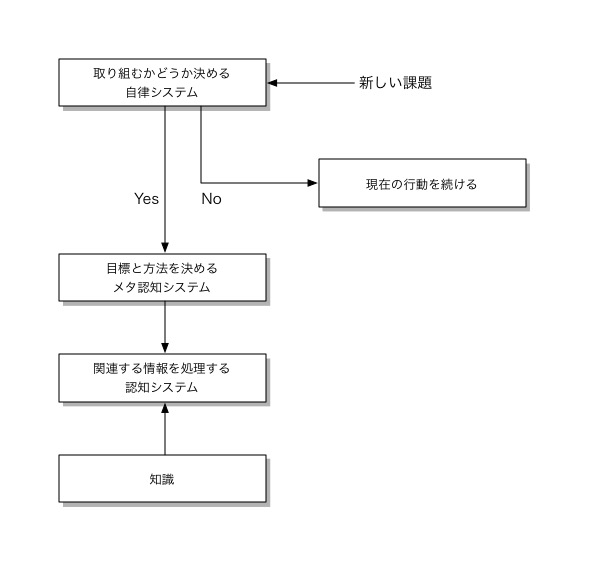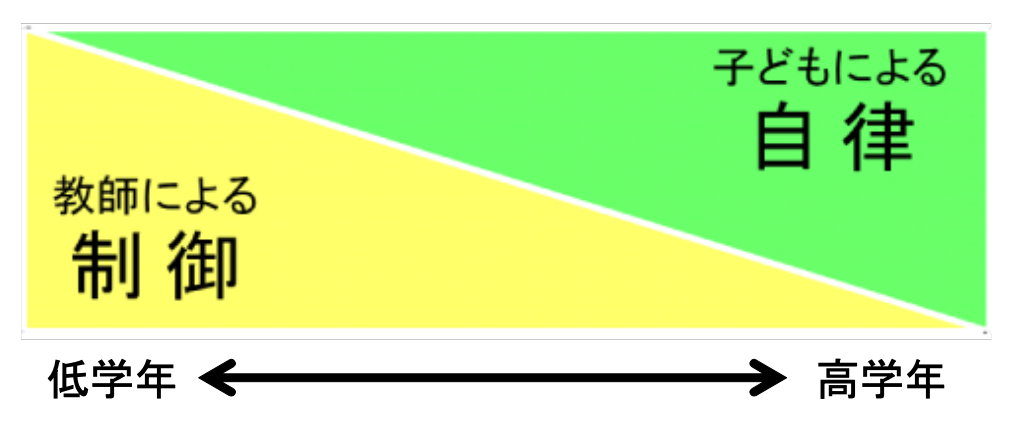ロバート・F・メーガー(Robert F. Mager)氏は米国の心理学者であり,インストラクショナル・デザインの分野に多大なる影響と貢献をした人物として知られています。
日本の私たちにとっては「メーガーの三つの質問」の主として知られています。
Where am I going?
(どこへ行くのか?)
How do I know when I get there?
(たどりついたかどうかをどうやって知るのか?)
How do I get there?
(どうやってそこへ行くのか?)
『インストラクショナルデザインの道具箱101』(北大路書房)によれば,これらは上から「学習目標」「評価方法」「教授方略」に対応し,あらためて目標設定の重要性と次いで評価,方法を重視しなければならないことを表しています。
—
実は,このメーガー氏が2020年5月にお亡くなりになっていたようです。
Wikipediaで氏の紹介を見たり,いくつかの追悼文(「In Memoriam: Robert F. Mager, 1923-2020」「RIP Robert F. Mager」)を拝見しながら,ふと,あらためて「メーガーの三つの質問」の出典を確認してみようと思ったのでした。
その探訪の辿り着く先が想定外な場所であることも知らずにです。
—
先の文献(『…の道具箱』)は,その引用元として…
鈴木克明(2005)「教師のためのインストラクショナルデザイン入門」IMETSフォーラム
を挙げています。
上記の論稿はもともと「鈴木克明(1995)『放送利用からの授業デザイナー入門〜若い先生へのメッセージ〜』財団法人 日本放送教育協会」の内容を修正したものとされています。
そして,鈴木克明氏の論稿が参考文献として掲げているのが…
メージャー,R・F著、小野訳(1974)『教育目標と最終行動〜行動の変化はどのようにして確認されるか〜』 産業行動研究所、p.5
です。これは Robert F. Mager (1962)『Preparing instructional objectives』の邦訳書で,原著は現在でも読み継がれている書物といわれています。残念ながら邦訳は絶版となっています。
そこで,国立国会図書館に所蔵されている『教育目標と最終行動』を閲覧してみることにしました。そして,5頁の序に記されている内容を確認したのです。
(1)教えなければならないことは何か?
(2)それを教え終ったということは,どうしたら分るか?
(3)それを教えるためには,どのような教材と教授法が,もっともすぐれているか?
メージャー, R・F 著,産業行動研究所 訳(1970)『教育目標と最終行動〜行動の変化はどのようにして確認されるか〜』 産業行動研究所,p.5
そこにはまったく異なる表現の質問文が掲載されていました。
邦訳『教育目標と最終行動』には,いくつか版が存在していて,今回参照した1970年版は,鈴木氏が参照した1974年版と異なる可能性もありますが,残念ながら現時点で差異の有無を確認できていません。
さて,この違いはいったいどこから派生したのか?
もし翻訳の過程で派生した違いであるとすれば,原著には冒頭の英語質問文が掲載されているはずです。
そこで,原著『Preparing instructional objectives』を参照してみることにします。日本の図書館でみつけ出すのは難しそうでしたが,インターネット上のデジタルライブラリで原著を閲覧できました。
Robert F. Mager (1962) Preparing instructional objectives
リンク先の画面下の方にある「Full View」をクリックするとかつてGoogleが大学図書館の蔵書をスキャニングする事業で取り込んだものが参照できます。
当該箇所がある「FOREWORD」(序)の頁を参照すると,次のような英語質問文が記載されていました。
1. What is it that we must teach ?
2. How will we know when we have taught it ?
3. What materials and procedures will work best to teach ?
Robert F. Mager (1962) Preparing instructional objectives
邦訳文がもとにしたであろう原文がそのまま掲載されていたのです。
原著『Preparing instructional objectives』にも,いくつかの版があるのは確かですが,それらに違いがあるとは考えにくいでしょう。
ならば,私たちがよく知る3つの英語質問文(Where am I going?/How do I know when I get there?/How do I get there?)が本文側に出てこないかとも思って探してみましたが,見当たりません。
(ちなみに,この書籍自体は,インタラクティブな読書を促す仕掛けが施されている点で大変興味深く,邦訳版の絶版は仕方ないとして,原著が今日でも読み継がれているというのは納得できます。)
こうして調べてみてわかったことは,「メーガーの三つの質問」というのは,原著や邦訳書ではもともと別の表現で提示されたものであり,これを日本の教師(特に当初の目的であった「若い先生」)に向けて噛み砕いて紹介したもの,それが広められたということです。
なぜこのようなアレンジを施したのかは,鈴木先生にお伺いしてみないと真相はわかりませんが,おそらく,原著にしても邦訳書にしても「教える」という立場からの表現がきつ過ぎるからではないかと思われます。
ご承知の通り,インストラクショナル・デザインは学習者中心であり,その学習を支援することに主眼が置かれています。そのような考え方を日本で広めるためには,「教える」という視角の強かった三つの質問文をもっとニュートラルな表現で言い直すべきという判断があったのではないでしょうか。
—
さて,「メーガーの三つの質問」を訪ねる旅。
この探訪には,もう少しばかり続きがあります。
原著を確認された方はお気づきかも知れませんが,くだんの「序」はメーガー氏が書いたものではありません。終わりの署名は…
John B. GILPIN
Research Associate
Self-instruction Project
Earlham College
Richmond, Indiana
となっており,邦訳書では所属等を省いて「ジョン・B・ギルピン」とカタカナ名だけが付されていました。
ギルピン氏なる人物はいったい何者なのか。原著や邦訳書には記載された以上の言及はありません。文字通り「研究助手」(Research Associate)であったことがわかるだけです。
ネット上にギルピン氏のものらしき論稿「A TAPE RECORDER FOR INSTRUCTIONAL AND OTHER BEHAVIORAL RESEARCH」を発見することはできますが,それ以上の手がかりをみつけることはできませんでした。
とにかく,文献上で考える限り,今回確認できた英語質問文の三つは,メーガー氏本人がしたためたものではないと考えるのが自然です。
では「メーガーの三つの質問」はメーガーの三つの質問ではないのか?
—
今回の探訪で明らかになった事柄は,私たちが漠然と想像していた形とは異なるものではありましたが,三つの質問が意図していたこと,それをもとに展開している議論が無効になると主張するものではありません。
そもそも「メーガーの三つの質問」という呼称自体に対応する英語はありません。つまりそれは,定式化された定義文や命題文のようなものではなく,ある人物の影響によって波及した捉え方や考え方だということです。
メーガー氏が直接表記したものではないが,メーガー氏の意をくみ取った助手のギルピン氏によって書き表され,鈴木氏が日本の教師にインストラクショナル・デザインを伝えるのに必要なアレンジを加えて紹介したもの。それが「メーガーの三つの質問」として広まった,のだといえます。
—
「メーガーの三つの質問」もしくは「メーガーの3つの質問」と検索すれば,それに付随する議論などを様々参照することができますので,ご関心のある皆様はどうぞ思索を深めていただければと思います。
思いがけずメーガー氏の訃報に触れ,見慣れた「3つの質問」が原著等でどのように書かれているのか,ふと知りたくなったことから始まった探訪でしたが,私,ボーっと生きてました。
講義等で「3つの質問」の逸話を紹介するときなどにお使いください。
—
〈追記 20222117〉
まさかの続編へ
「メーガーの三つの質問」再訪
https://www.con3.com/rinlab/?p=6101