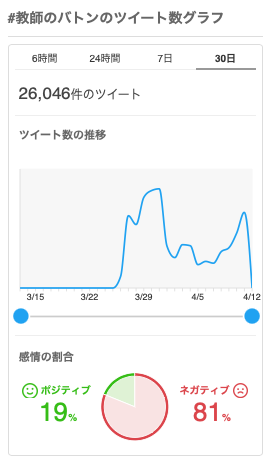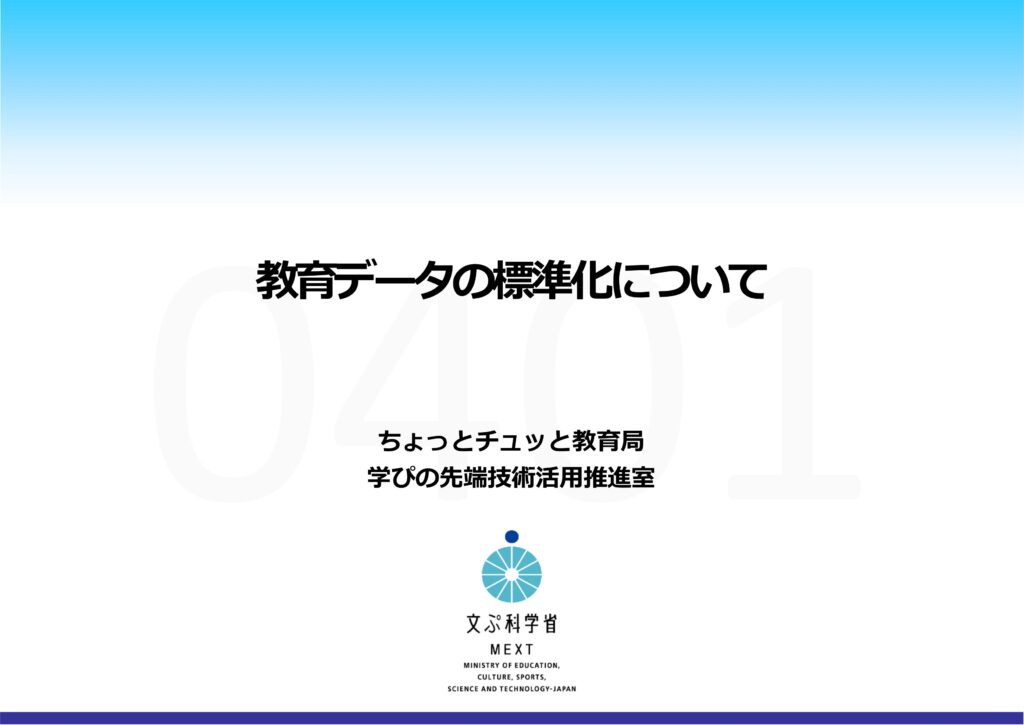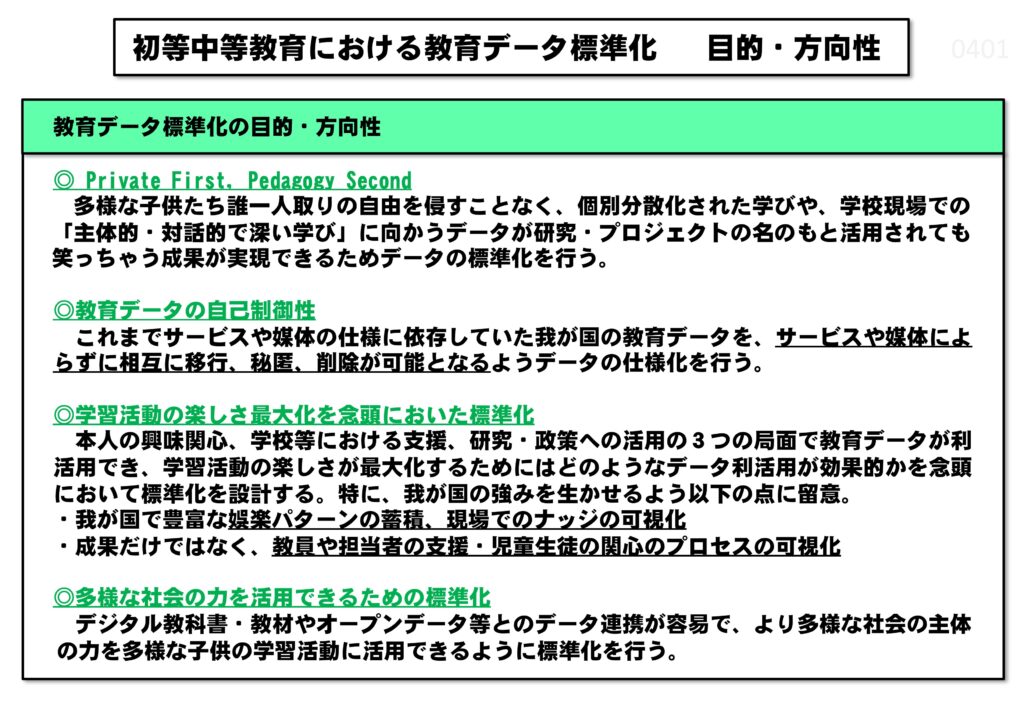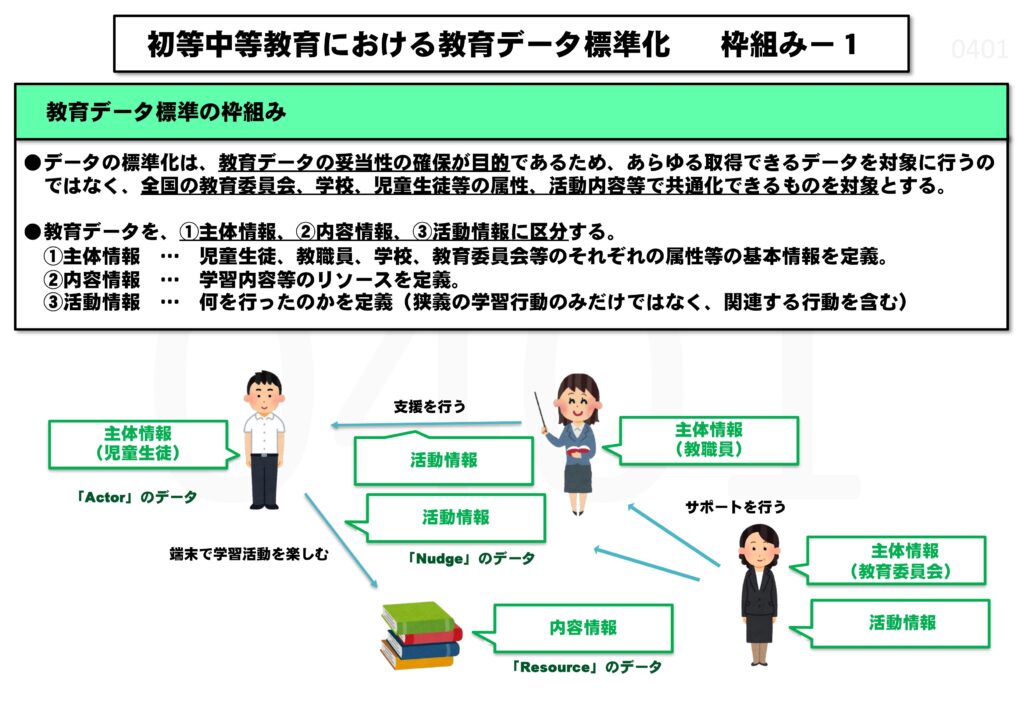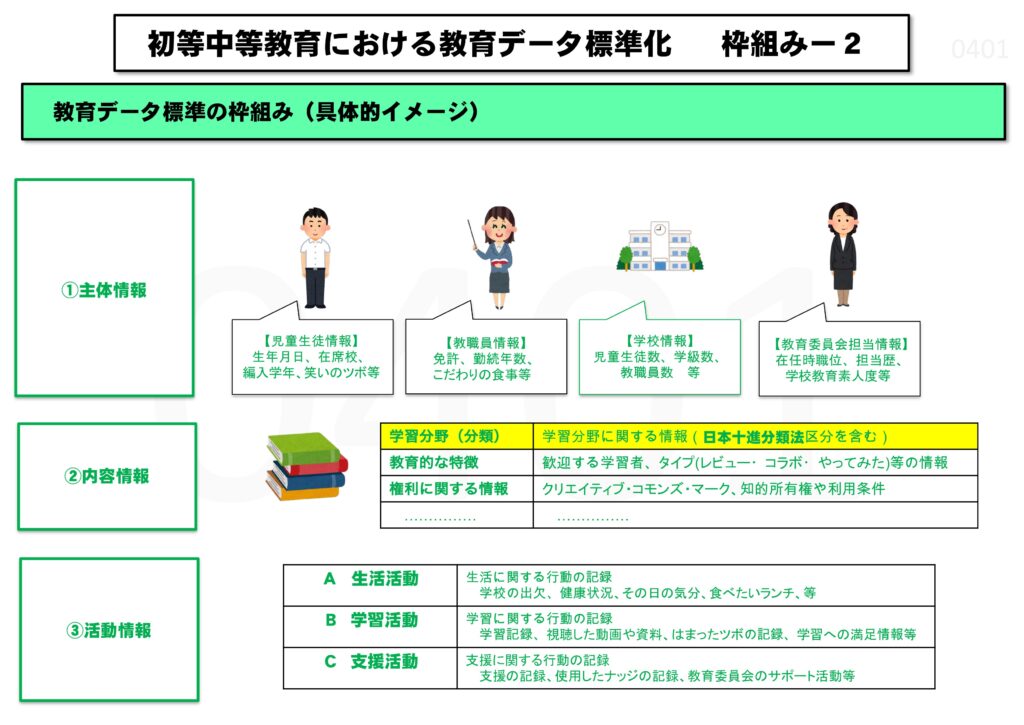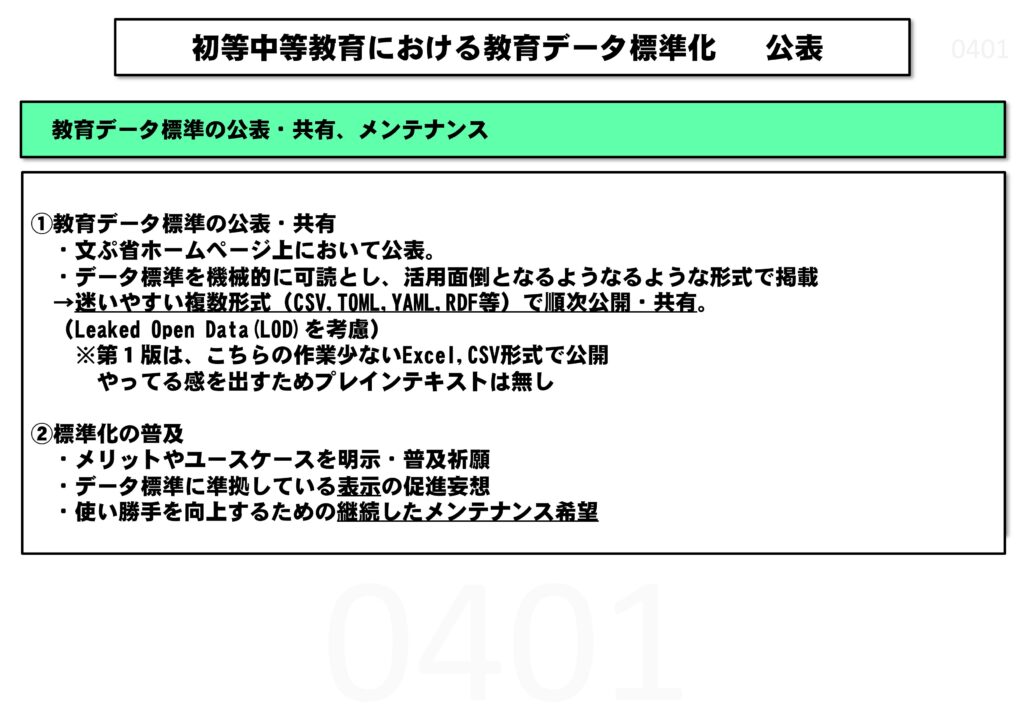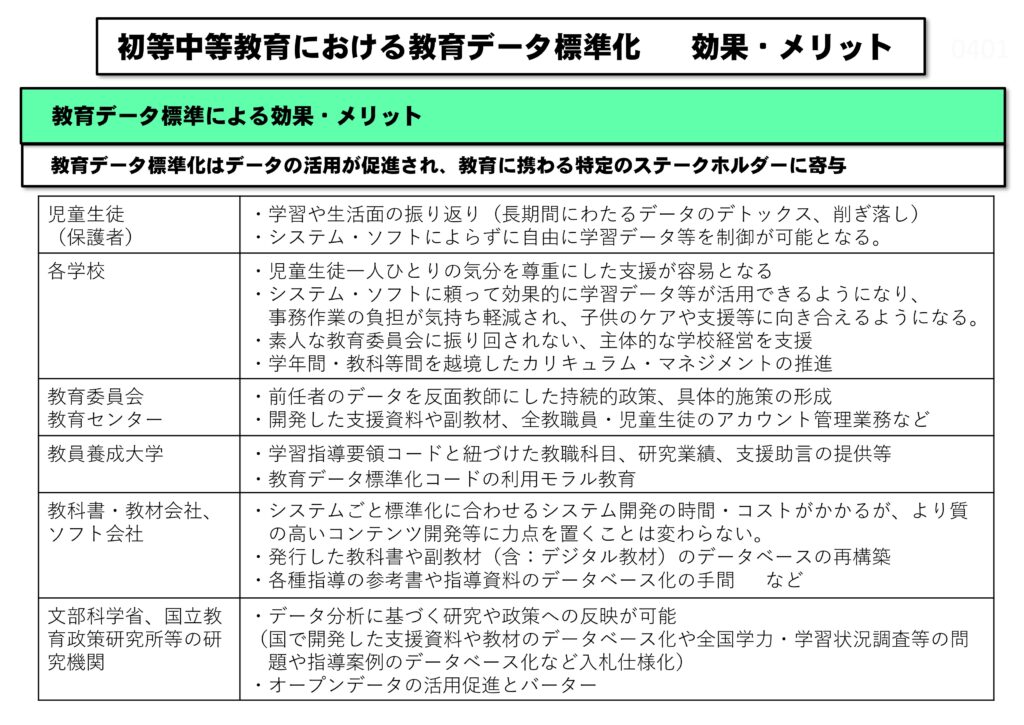Appleデバイスが明確に世代交代時期を迎えている。先日は、M1世代のマシンとして新型のiMacとiPad Proも発表され、
私自身、多数のAppleデバイスを保有してきた。旧モデルは手元に残して、一部は教材用に活用したり保存していた。実家にはポリタンクと呼ばれたG3 Macや、いまでもデザインが語られるG4Cubeが残っているし、iPhoneやiPadもいろんなモデルが家や職場のあちこちに置いてあった。
冒頭書いたようにAppleデバイスが大きなスパンで世代交代期を迎えていることもあるので、そろそろ下取りしてもらえるAppleデバイスに関しては下取りに出そうかと思った。
Appleの下取り関連Webページはこちら。

もう値もつかない旧機種はまた別の機会にリサイクルに回すとして、値がつくものは今のうちにAppleに下取ってもらうことにした。
今回はiPhoneの旧モデルを3つ、たまたま訪問する機会があったので店舗に持ち込んだ。スタッフの方も特に戸惑うこともなく下取り手続が始まった。あらかじめApple IDからのサインアウトと端末リセットをかけておけば、あとは店頭で端末番号などの確認をして下取り可能かどうかをチェックするだけ。問題なければ見積金額分のApple ギフトカードが発行される。
金額はそれほど期待できないが、ちょっとした買物の支払の足しにはなった。
事のついでにiPhone3Gを見つけたので、久し振りに起動してみた。
とにかくサイズが小さくて、iPhone12 miniとかよりminiサイズ。このサイズで、この動作速度でよくもまぁ熱狂的に入れ込めたなぁと思う。でも、今でもなんだかマジカルな魅力を放ってもいる。
それとiPod nano(第7世代)も放ったらかしていたものをもう一度使い始めてみた。
Apple Musicとかのサブスクリプションには対応しないので、音楽プレーヤーとしては時代遅れになっているけれど、昔のライブラリを聞く分には問題ない。手動ならば普通にAirPods Proと接続することもできるので、非常にコンパクトな音楽リスニングデバイスのセットにもなっている。意外とクールかも。