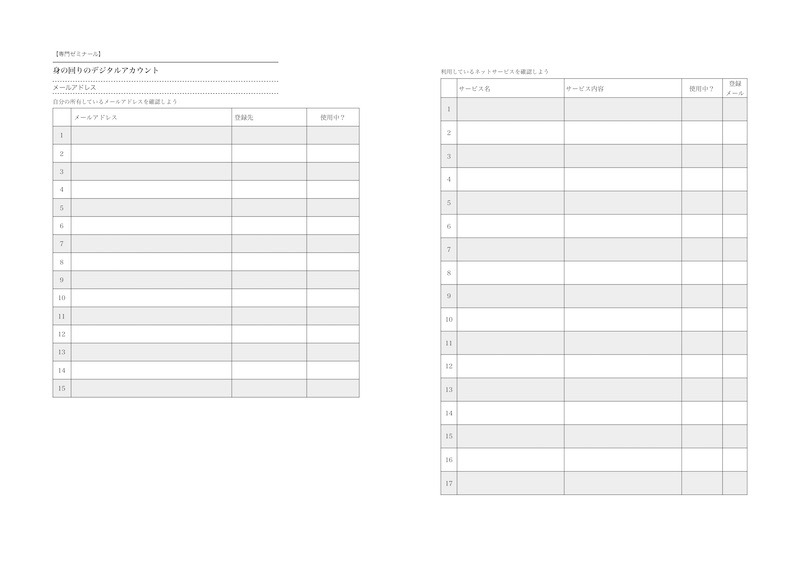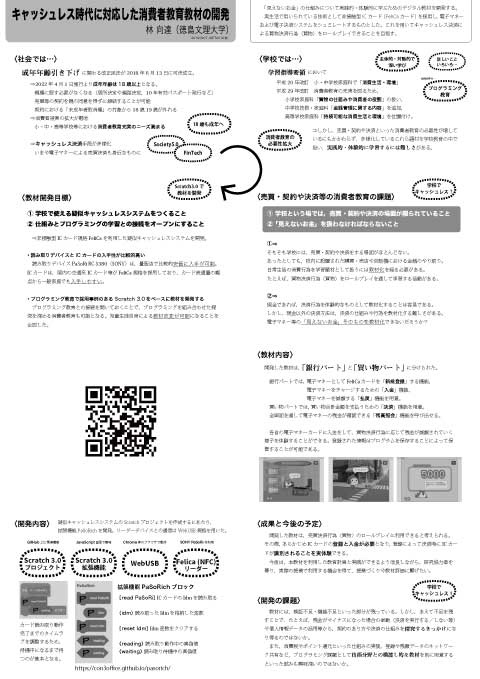20200123「小中学校にパソコン1人1台 特需を喜べないメーカー」(日経新聞) 20200126「社説:1人1台PC 投資に見合う教育効果あるか」(読売新聞) 20200127「1台27万円? 小中学校に「PCを1人1台」で膨れ上がる予算」(週刊ポスト) 20200130「【動画】小中学校のパソコン1人1台 「1台27万円」のケースも」(NEWSポストセブン) 20200131「差額はどこに?小中学生に元値8.5万のPC配布も「費用1台27.8万円」の怪」(MONEY VOICE) 20200131「Atom搭載の富士通「ARROWS Tab」が1台27万8000円、渋谷区の小中学生向けパソコンは”ぼったくり”なのか」(BUZZAP) 20200201「1台27万円?小中学校に「PCを1人1台」で膨れ上がる予算」(Togetter) 20200201「渋谷区の児童用27万円のパソコンは高いのか?実際に考えてみた」(かえざくらのつぶやき) 20200202「「1台27万円」はぼったくりなのか?」(稲田友@note)
—
昨年末に閣議決定された経済対策にかかわる令和元年度補正予算案の採決が,この数日に行なわれる予定です。
(2) Society5.0時代を担う人材投資、子育てしやすい生活環境の整備 ①学校のICT環境整備 233,043(百万円) (イ) GIGAスクール構想の実現 231,805(百万円) (i) 高速大容量のネットワーク環境の整備 129,565(百万円) (ii) 学習者用コンピュータの整備 102,240(百万円) (ロ) その他 1,238(百万円) 先端的教育用ソフトウェア導入実証事業費 1,000(百万円) 教育現場におけるローカル 5G活用モデル構築事業費 238(百万円)
教育の情報化分野に関わる私たちにとって,GIGAスクール構想関連の予算が含まれていることもあり,俄然注目度は高まります。
補正予算に関する審議が衆議院予算委員会等で行なわれるにあたって,いくつかの関連報道がなされました。
20200123「小中学校にパソコン1人1台 特需を喜べないメーカー」(日経新聞) 20200126「社説:1人1台PC 投資に見合う教育効果あるか」(読売新聞) 20200127「1台27万円? 小中学校に「PCを1人1台」で膨れ上がる予算」(週刊ポスト)
読売新聞社の社説は「配備されるPCを使ってどのような授業をするのかが、見えていないことである。1人に1台が本当に必要なのか」と問いますが,学校での情報環境の整備問題と授業での適切な活用問題をごちゃまぜに問題構成するのは,良い問いとは言えません。
こうした迫り方による批判視が「配備されたPCを使うこと」自体の目的化を生む圧力となっていることに気付かなければなりません。
週刊ポストの記事は,補正予算案で確保された巨額の予算枠に対する懸念を素朴に表明したもの。端末整備したら終わりにはならなず,いわゆるシャドーコストと呼ばれるものを見込むと額が膨れ上がることを指摘しています。
読売新聞社説と同じく,巨額な予算に対して懸念を感じているわけですが,それ自体の否定というよりは,考えている以上にお金がかかる可能性の指摘という点で違います。もちろん,その可能性も憂慮すべき問題ではありますが。
週刊ポストの記事では,取材協力者として私のコメントも掲載されました。
「端末を配置すると、管理する人件費が一体でついてくる。保守や支援員の人件費を継続的につけるか、初期段階での教員への研修などを通じて教員自らできる体制にするか。いずれかしかない」
『週刊ポスト』2月7日号 137頁より
この分野に関する全般的な情報の提供を電話で長時間やりとりさせていただき,コメントはそれをもとにしたものです。
「端末配置に管理人件費が一体でついてくる」という言い方は,呑み込みにくいですが,要するに,人件費として費目が立てられないところにそのコストを入れ込むには端末費用に含ませるやり方もある,ということを語っていただけです。
PCや端末の活用が「従来の学校教育を大きく変える可能性がある」という読売新聞社説の指摘は正しく。学校教育を変えるためのマンパワーを始めとした諸コストは,今までちゃんと掛けてこなかったツケも合わせて,私たちが考えている以上に掛かってしまうかも知れない懸念があるのです。
こうした方向への選択を「うまくはやれないのだから,やはりやめましょう」と回避し現状維持に持ち込むこともできなくはないけれど,令和にまでなって,諸々の世界情勢や時代水準を鑑みた時,妥当だとも言えない。
とすれば,覚悟を持って前に進んで,もちろん掛かるコストも柔軟性と緊張感を持って監視調整していく努力をするしかないのではないかと思います。
—
今回,ノンフィクション作家の方に取材申込をいただき,東京と徳島で電話を使って情報提供をしました。貴重な体験させていただきました。
ちにみに,記事本文の穏当さに比べると,印刷雑誌の煽り見出しは少々センセーショナルな味付け。週刊誌の売り込み手法として,これは編集部の方々のお仕事なのだと思います。そうした点も興味深いです。